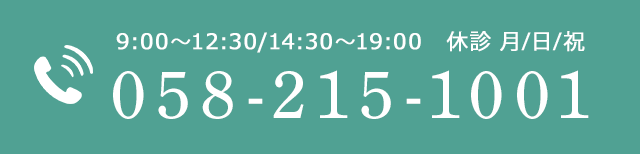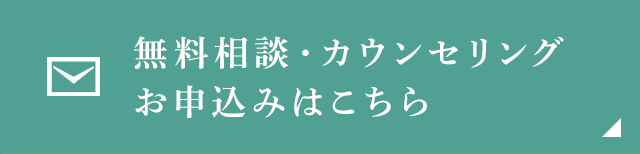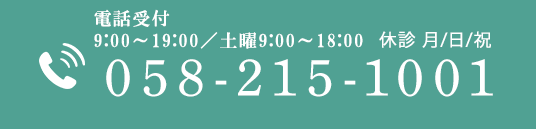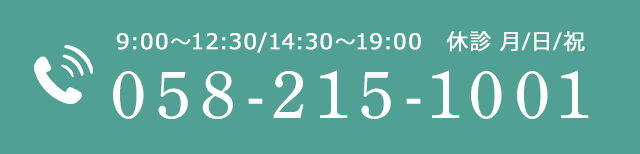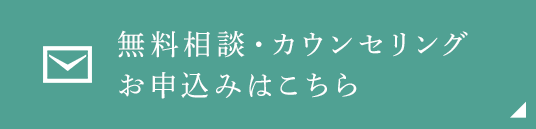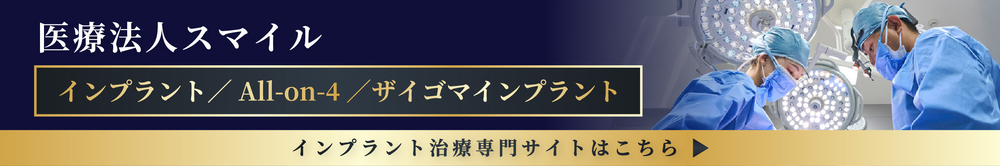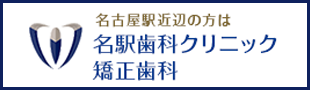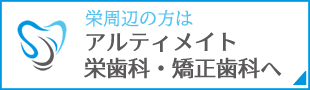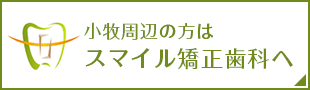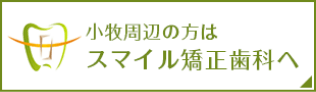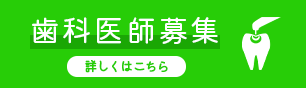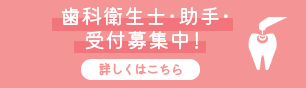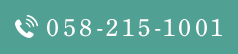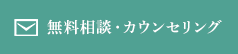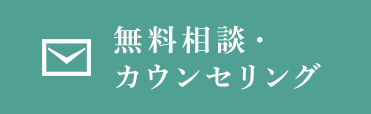-
インプラントは医療費控除の対象?利用する際のポイントや申請方法を解説
2024.09.25更新
「インプラント治療は医療費控除の対象になるの?手続き方法を知りたい」という疑...投稿者:
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2026年01月 (1)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (4)
- 2025年10月 (4)
- 2025年09月 (5)
- 2025年08月 (5)
- 2025年07月 (5)
- 2025年06月 (5)
- 2025年05月 (5)
- 2025年04月 (5)
- 2025年03月 (1)
- 2025年02月 (1)
- 2025年01月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年09月 (1)
- 2024年08月 (1)
- 2024年04月 (1)
- 2023年03月 (4)
- 2023年02月 (3)
- 2023年01月 (3)
- 2022年12月 (6)
- 2022年11月 (6)
- 2022年10月 (5)
- 2022年09月 (6)
- 2022年08月 (3)
- 2022年07月 (6)
- 2022年06月 (6)
- 2022年05月 (2)
- 2022年04月 (3)
- 2022年03月 (3)
- 2022年02月 (3)
- 2022年01月 (3)
- 2019年05月 (1)
カテゴリ
- その他 (0)
- 設備 (0)
- ザイゴマインプラント (1)
- オールオンフォー (11)
- インビザライン (10)
- インプラント (32)