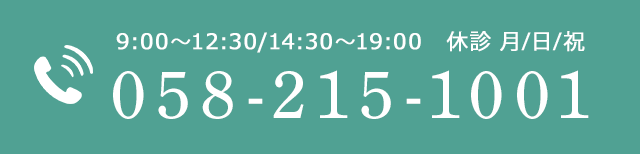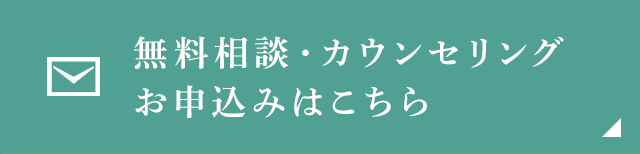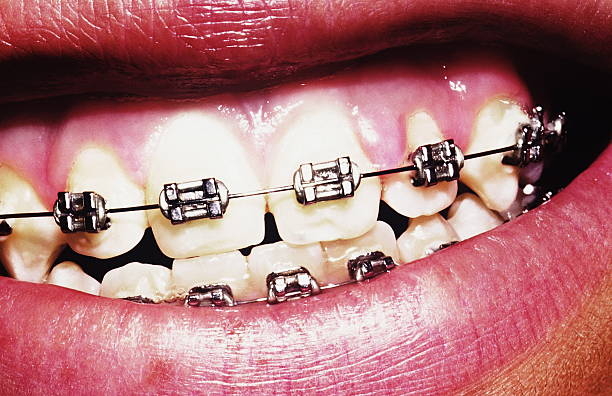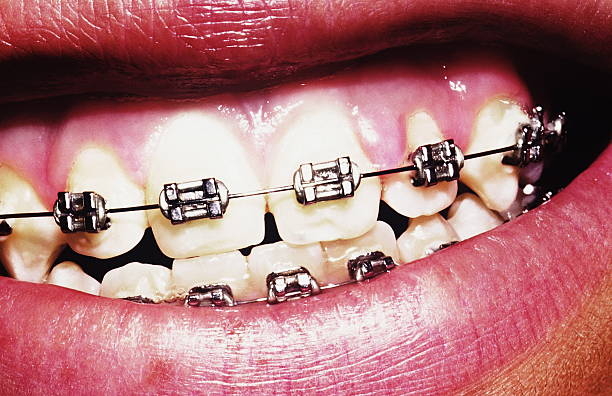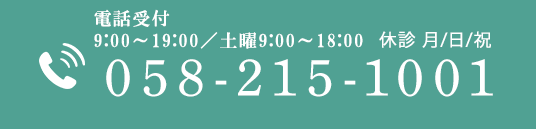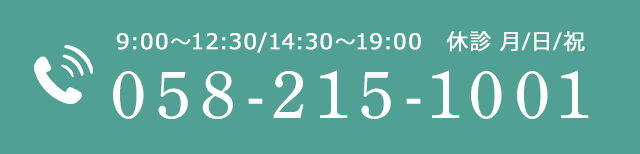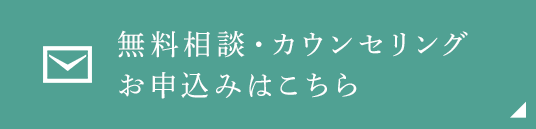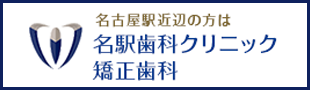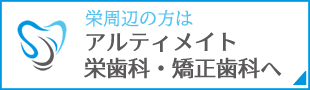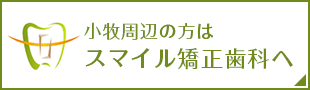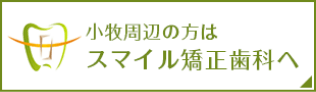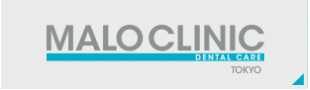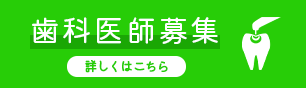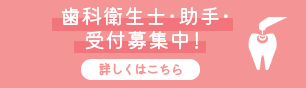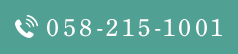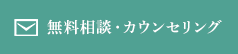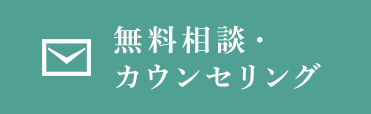前回に引き続き「奥歯のインプラント」について詳しく解説します。治療のメリットやデメリットを中心にお話しするので、補綴治療を予定している方はぜひご一読ください。
メリット
インプラントには、ブリッジや義歯にない魅力が複数存在します。まずはメリットを理解し、補綴治療の選択肢の一つとしてぜひ検討してください。
1.天然歯に近い噛み心地を実現できる
義歯は約2~3割、ブリッジは約6割程度の噛み心地を実現できるといわれています。
インプラントはそれ以上で、天然歯に負けない噛み心地を実現できるのだとか。食事のときに、違和感なく食事を楽しめるでしょう。
2.痛みや違和感が比較的少ない
義歯に比べると、痛みや違和感が少ないのも魅力の一つです。義歯は土台がないため、強く噛むと歯茎へ触れて痛みが出やすくなるでしょう。歯に合わない義歯を付けていると、より痛みが生じやすくなります。
一方インプラントは、歯槽骨へ埋め込んだ土台に人工歯がある状態です。強く噛んでも、痛みや違和感が出る心配がないでしょう。何かの拍子にずれることも、まずありません。
3.噛み合わせのバランスが正される
噛み合わせの良し悪しは奥歯の高さによって決まるため、何らかの理由で奥歯を失くすと咬合力が偏りバランスが崩れます。肩こりや頭痛、顔のゆがみなどを起こす恐れがあるでしょう。
ほかの補綴方法で治療を行うと、咬合力の不足から偏りを改善できないかもしれません。しかしインプラントは「天然歯に近い噛み心地を実現できる」という特性から、時間が経つとともにバランスを整えられる可能性が高いです。
4.発声や発音がしやすくなる
奥歯を失うと、欠損部から息が漏れて「ラ行」や「イの段」の発音が難しくなります。インプラント以外の方法でも改善が見込めますが、義歯の場合は話している途中にずれることが懸念されます。しっかりと固定されるインプラントであれば、その心配なく会話を楽しむことが可能です。
5.顎骨の吸収を予防できる
歯を失くすと、歯槽骨が歯根を通じて刺激を受けることがなくなります。時間の経過とともに歯槽骨がやせていき、骨の吸収が徐々に進行するでしょう。
歯根のないブリッジや義歯ではこの問題を解決できませんが、インプラントであれば人工歯根と顎骨ががっちりと結合します。刺激が伝達し、歯の健康をキープできるでしょう。
デメリット
続いてはデメリットを紹介するので、両者を理解したうえでご自身にとって最適な治療法を選びましょう。
1.保険が適用できない
インプラントは保険が適用できないため、治療費が高額になる傾向にあります。埋入本数が増えるにつれて、治療費がかさんでしまうでしょう。
一方でブリッジや義歯は、選ぶ材質によって保険適用内の治療ができます。
予算がある方は、ほかの補綴方法を検討するのもよいかもしれません。
2.ある程度の通院が必要
外科手術でインプラント体を埋め込むと、結び付くまでに約3ヶ月の経過観察が必要です。
さらに骨造成が必要となると、1年ほどかかる可能性もあります。
仕事や育児が忙しい方にとっては、通院がネックだと感じるかもしれません。
3.骨造成が必要になるケースもある
治療前の検査で厚みや骨量不足が発覚した場合、まずは骨造成を行わなければなりません。
骨造成や骨移植に対応していないクリニックの場合は、転院が必要になるでしょう。
まとめ
岐阜駅前歯科クリニック・矯正歯科では、患者さまのさまざまなニーズにお応えできるよう最先端の技術や設備を積極的に取り入れています。
事前検査で骨が薄いことが発覚した場合は、サイナスリフトやソケットリフト、そして骨自体の再生を促すGTR法などを用いて十分な骨量を確保します。
年間約500本のインプラントを埋入している、経験豊富な歯科医師が担当しますのでご安心ください。